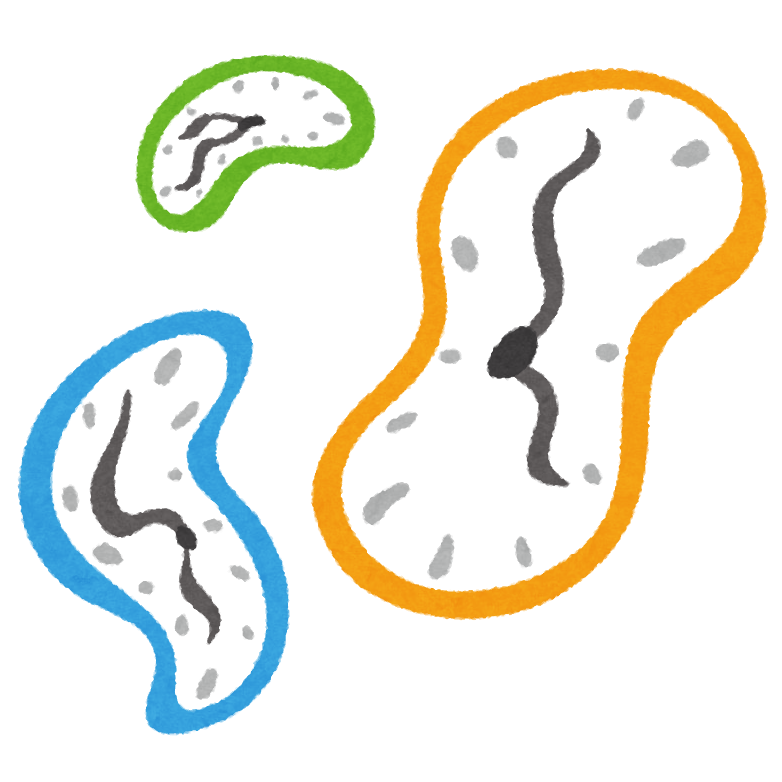タイムマシン
H・G・ウェルズの作品で「タイムマシン」が最初に読んだSF小説(1895年発表)である。タイムマシンに乗って紀元802,701年の未来に到達する。そこではイーロイと自称する単一の人種が幸福に暮らす、平和で牧歌的な桃源郷のような世界であった。知能的には退化して幼児のようであり、その生活にはいさかいも争いもないように見える。しかしイーロイのユートピアは偽りの楽園であった。人類の種族が2種に分岐しており、裕福な有閑階級は無能で知性に欠けたイーロイへと進化した。イーロイは身の丈約4フィート(約120センチ)に、ピンク色の肌と華奢な体格、巻き毛と小さな耳と口、大きな目をもつ種族で男女共に非常によく似た女性的な穏やかな姿をしている。イーロイは高く穏やかな声で、未知の言語をしゃべるが、知能的には退化して幼児のようであり、その生活にはいさかいも争いもないように見える。時間旅行者は、川でおぼれかけたイーロイの女性ウィーナを助けて仲良くなり、彼女を通して、あるいは自分自身の様々な体験から、次第にこの未来世界の真実を知る。
イーロイのユートピアは偽りの楽園であった。時間旅行者は、現代(彼自身の時代)の階級制度が持続した結果、人類の種族が2種に分岐した事を知る。裕福な有閑階級は無能で知性に欠けたイーロイへと進化した。抑圧された労働階級は地下に追いやられ、最初はイーロイに支配されて彼らの生活を支える為に機械を操作して生産労働に従事していたが、しだいに地下の暗黒世界に適応し、夜の闇に乗じて地上に出ては、知的にも肉体的にも衰えたイーロイを捕らえて食肉とする食人種族モーロックへと進化した。
モーロックとの死闘やウィーナの死、いくつかの探索を経て、時間旅行者は更に遠い未来へと旅立つ。滅亡しつつある地球に残る最後の生物たちを目撃した時間旅行者は、現代に帰還し、友人達にこの物語を語る。その後に再び時間旅行を試みた時間旅行者は、時の流れの中に永遠に姿を消す。
H・Gウェルズ
作者のH・Gウェルズ(1866~1946)はイギリス人で、教員を目指すが、教育界の保守的な体質と自身の病気により道を阻まれ文筆活動へ進む。やがてジャーナリストとなり「ベル・メル・ガゼット」や「ネイチャー」に寄稿する。
1890年から1900年代初頭にかけて「タイムマシン」(1895年)をはじめ「モロー博士の島」(1896年)「透明人間」(1897年)「宇宙戦争尾」(1898年)など現在でも有名な作品を発表する。科学知識に裏打ちされた空想小説が多く、ウェルズ自身は「科学ロマンス」と呼んだ。
ウェルズは日本国憲法の原案作成に大きな影響を与えたとされる。特に日本国憲法9条の平和主義と戦力の不保持は、ウェルズの人権思想が色濃く反映されている。しかしウェルズの原案から日本国憲法の制定まで様々な改変が行われたため、憲法9条の改正議論の原因のひとつとなっている。またこの原案を全ての国に適用して初めて戦争放棄ができるように記されており、結果として日本のみにしか実現しなかったことで解釈に無理が生じたと言われている。
宇宙戦争
19世紀6月の金曜日の未明、イングランドのウィンチェスター上空で緑色の流れ星が観測され、天文学者のオーグルビーは、流れ星がロンドンの南西ウォーキング付近に落ちているのを発見。それは直径30ヤード(27.4メートル)ほどの巨大な円筒だった。夕方、主人公「私」を含めた見物人が群がる中、円筒の蓋が開いて醜悪な火星人が現れた。オーグルビーは、王立天文官ステント、新聞記者のヘンダーソンらと共に急遽<代表団>を結成。火星人がいかに醜悪な外見でも、何らかの知性を持っている事を示そう、という理由だが、彼らが円筒に近づいた途端、目に見えない熱戦が人々を焼き払った。熱戦は恐るべき威力で、人物や動物を含め、周囲の木々や茂み、木造家屋などが一瞬で炎に包まれた。夜、英国軍が出動したが、真夜中過ぎに火星人の第二の円筒が落下する。
土曜日の午後、軍地の攻撃が始まったが、夕方には「私」の自宅付近も火星人の熱線の射程内となる。「私」は近くの店で馬車を借り、妻を引き連れ彼女のいとこが住むレザーヘッドへ逃げる。その馬車を返す途中、真夜中過ぎに火星人の第三も円筒が落下。家より背が高い3本脚の戦闘機械(トライポッド)が登場し、破壊の限りを尽くす。馬車を借りた店の主人も死に、出動した英国軍も全滅。自宅に生き残りの砲兵が逃げ込んで来た。
日曜日の朝、二人はロンドン方面へ避難を開始。午後、テムズ河畔に火星人の戦闘機械5体が現れるが、砲撃で戦闘機械の1体を撃破。一旦は撃退に成功する。その戦闘の混乱で「私」は砲兵とはぐれてしまい。夕方、教会の副牧師と出会う。一方、火星人はその夜から、液体のような黒い毒ガスと熱線を使う攻撃に戦法を変更し、軍を撃破してロンドンへと向かう。
月曜日の未明、ロンドン市民はパニック状態で逃げ惑う。軍隊は総崩れ。英国政府は「もはや火星人の侵攻を阻止し、ロンドンを防衛するのは不可能である。黒い毒ガスからは逃げるより他に無い。と避難勧告を出す。これを知ったロンドン在住の「私」の弟も避難を開始。暴漢に襲われていた女性らを助け、ともに馬車で英仏海峡の港を目指す。港にたどり着いたのは水曜日の午後だった。3人が乗った蒸気船が出港すると、火星人の戦闘機械が3体現れる。沖にいた駆逐艦サンダーチィルドは、戦闘機械目がけて突進し、砲撃で撃破。2体目に迫る途中、熱線を受けて大爆発するも、体当たりで2体目に迫る途中、熱線を受けて大爆発するも、体当たりで2体目も撃破。3体目の戦闘機械は逃げ去り、「私」の弟たちの乗った船は英国から脱出した。「私」は、出逢った副牧師と共に、日曜日の夜から黒い毒ガスを避けて空き家に避難していた。翌日の夕方、火星人が去ったので、2人は逃避行を続け、ロンドン近郊の空き家にたどり着くが、真夜中、突然近くに火星人の円筒が落下。廃屋に閉じ込められてしまう。日数が過ぎるうちに「私」は副牧師と対立。極限状態に陥り、大声を出す彼を殴り倒す。その物音を気付かれ、火星人にあと一歩で捕まりそうになったが、何とか生き延びる。15日目の朝、辺りが静まり返っている。思い切って外に出ると、火星人らは姿を消していた。
「私」は以前出逢った砲兵と再会し、人類が負けた事と将来の事について話し合う。
砲兵と別れたあと静寂に包まれたロンドンに入った「私」は、そこで戦闘機械を澪つける
死を決意し近づいていくが、そこで見つけたものは火星人たちの死体だった。彼らを倒したのは、人間の武器や策略ではなく、太古に神が創造した病原菌であった。地球の人間と違って、これらの病原菌に対する免疫が全くなかった火星人」たちは、地球で呼吸し、飲食を始めた時から死にゆく運命だったのである。
やがて人々は舞い戻り、復興が始まる。
「私」は約4週間ぶりに自宅に戻る。幸い自宅はほぼ無事だった。外で話し声がする。
窓から見ると、それは妻と彼女のいとこだった。