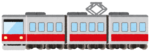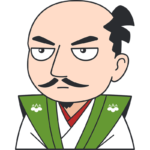三千里樋
我が家の前を流れていたドブ川は三千里樋といい、南江口、大同村、小松村を通り、国次町北より三国村、十八条町。新高村、加島町、(淀川区)を経え、大和田町(西淀川区)の北に達する本流と、大同牛腸より豊里町字能條を経て
、淀川右岸堤防に沿い豊里菅原町・南方・十三を経て塚本に至る支流を持つ、用水引用の大用水ができました。本流と支流の総延長は、約26キロメートル余りに及び三千里樋は淀川右岸の田畑1,800町歩(約18平方キロメートル)を潤す誘致の樋門となりました。(本流水路は、大正6年10月、下新庄で神崎川堤防が決壊したため瑞光寺前より西へ引江まで一直線に変更されました。
地図で見たら新大阪駅近くまで大隅~下新庄まで新幹線と重複しています。
治水が悪いこの地域の用水を庄屋たちが申し出たが聞き入れられずやむなく自前で灌漑工事を行なったのが幕府の怒りにふれ、切腹を申し渡され、抗議の意味を込めて江戸の彷徨に向けて腹を切ったという。
その無念を祀った神社がユアライフ新大阪作業所から新大阪駅道中に祠としてひっそりとたっている。
三千里樋は戦後上流に市営住宅が出来、下水道水を浄化しないで流したため、蛍が飛んでいた水質がヘドロまみれになった。私の記憶にはメタンガスの泡がボコボコ音をたてる不気味なドブ川で、ネズミや蛇しかいない、あとは猫や犬の腐乱死体が捨ててあるような様子になっていた。
江口の君堂(寂光寺)
私の母校の大隅東小学校の隣には源流の江口には江口の君堂(寂光寺)があった。
平資盛の娘で平家没落後江口で遊女になり、出家したといわれる光相比丘尼が元久2年に開基したとされている。
西行法師が当地を通行中ににわか雨に会い、雨宿りを江口の君に請うたところ断られました。
西行法師の歌
新古今和歌集
天王寺に詣で侍りけるに、俄かに雨のふりければ、
江口に宿を借りけるに、貸し侍らざりければ、
よみ侍らける
西行法師
世中いとふまでこそかたらめかりの
宿りを
おしむ君かな
返し
遊女妙
世といとふ人としきけばかりの宿に心とむなと
思ふばかりぞ
こうして歌を読み返しながら、一夜を明かしたというお話。
どうも遊女というのがよくわからなくて、売春婦のことかと思っていた。もう少し違っていて気に入ればそうゆうこともするみたいになってしまうらしい。小学校の先生にちゃんと聞いておくべきだったと思う。答えに窮したとは思うが。古今和歌集にふれる良い機会である。しかし歌というものの奥ゆかしさに感心したものである。